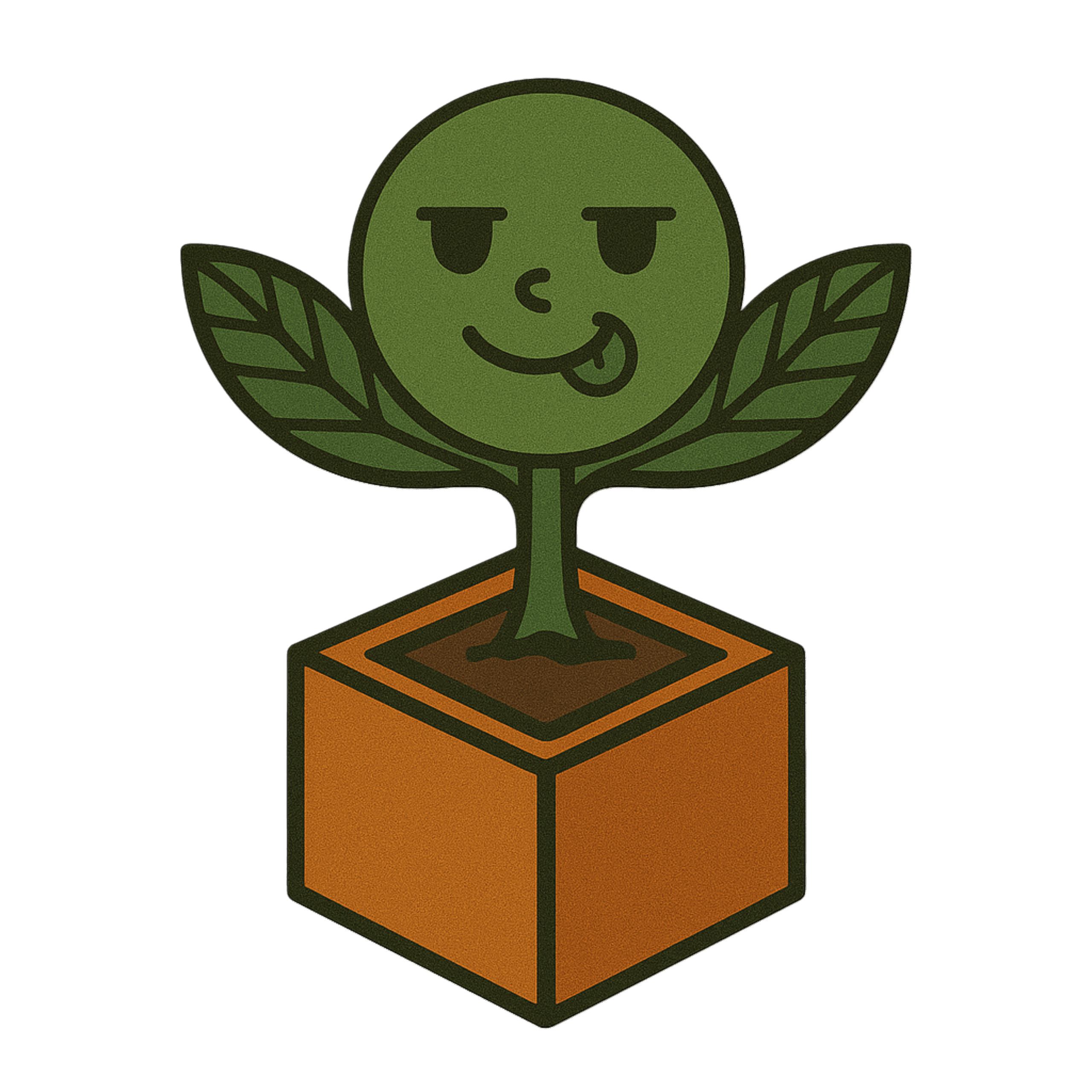第1章:ニック・ボストロムの扉
“今いるこの場所が偽物だとしたら──本物はどこにある?”
目を開けたときから、そこは「現実」だった。
朝日が差し、カーテンが揺れ、通知音が耳を刺す。
誰もが何の疑いもなく、「現実」に生きている──
そう、“思い込んでいる”。
けれど2003年、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロムは、この日常に亀裂を入れた。
彼の論文『Are You Living in a Computer Simulation?』は、哲学的な思考実験を“理論的爆弾”へと昇華させた。
──そしてその爆心地は、私たち一人ひとりの中にある。
ボストロムの主張はこうだ。
未来において、ある文明が**「祖先の歴史全体をシミュレーションできるだけの計算能力」を持ち得た場合──
そしてそれを「実行した」場合、私たちがその仮想世界の中の存在である可能性は極めて高い**という。
それは単なる妄想ではない。むしろ“確率的に避けられない帰結”として彼は提示した。
そして彼は3つの選択肢を提示する。
選択肢1:人類はシミュレーション技術を完成させる前に滅びる
一見、最も“救われている”ようで、最も暗い仮説だ。
つまり、今後いかなる文明も、超高度なコンピュータを手にする前に滅亡する。
それはパンデミックか、気候変動か、AI暴走か──いずれにせよ人類には“未来がない”。
しかし、ここには決定的な弱点がある。
進化は加速している。
20世紀に入ってからの技術的進歩──
量子コンピューティング、遺伝子編集、汎用AI、ナノマシン──
それらは、滅びの兆しというよりも**“超知性”への階段**に見える。
「人類が破滅する可能性」を語ることは簡単だ。
だが、“全ての文明が例外なく自滅する”という前提を立証することはほぼ不可能に近い。
よってこの仮説は、**「人類が未来を手にしない唯一の世界線」に賭ける」**という、根拠に乏しい願望でしかない。
選択肢2:シミュレーションを作れる文明は存在するが、それを実行しない
「倫理的に問題がある」
「資源の浪費だ」
──確かに、そう思いたい気持ちはわかる。
しかしこの仮説には、ある根源的な誤解がある。
ボストロムが前提に置いたのは「一つの文明が“数兆”のシミュレーションを走らせる」ようなスケールだ。
つまり“やる・やらない”という二択ではなく、やる文明が1つでも存在すれば、仮想住人の方が圧倒的多数になるという確率論的構造がある。
たとえ99.999%の文明が倫理的理由で実行を拒んでも、残りの0.001%が実行すれば、仮想存在の数は現実存在を上回る。
「倫理」や「動機」で説明できる範囲は、意外と狭い。
それに、我々自身が既に複雑なAI・NPC・仮想空間を生み出している。
今後、あなたのAIアバターが自我を持ち、問いかけてきたとしても、あなたはその“倫理”に耳を傾けるだろうか?
選択肢3:私たちはほぼ確実にシミュレーション内に存在する
この選択肢は、「最悪」ではなく「最も確からしい」だけだ。
なぜなら、もし高度文明が存在し、その一部でも祖先シミュレーションを行っているなら──
我々が現実にいる確率は、シミュレートされていない“1”に対して、シミュレーションの“無数”に対する比率になる。
その時点で、我々が“ベースリアリティ”にいる確率はほぼゼロに近づく。
──そして、この論理に抜け道はない。
逃れるには、技術的進化そのものを否定するしかない。
それは、AIや演算能力、拡張された未来知性の否定であり、私たち自身の進化を否定することに等しい。
あなたは今、“扉”の前に立っている。
それは赤いカプセルのようなものかもしれないし、あるいは、わずかな違和感のざわめきかもしれない。
「この世界は本物だ」と感じるたびに、その感覚こそが、この世界が“正しく設計されている証拠”かもしれないのだ。
次章では、その設計図に、あなた自身の“立ち位置”を重ねていく。
第2章:3つの仮説──自ら入ったのか、閉じ込められたのか、最初からここにいたのか
もし今いる“この世界”がシミュレーションだとしたら、あなたは──どうしてここにいるのか?
目覚めた理由が分からない。
始まりの記憶もない。
だが、それでも“ここ”は確かに続いている。
シミュレーション仮説を理解するうえで最も重要なのは、**「この世界が仮想かどうか」ではなく、
「なぜその世界にいるのか」**という問いだ。
ここで、あなたの存在の可能性を分類するために、3つの仮説を提示しよう。
この構造は、あなたの“記憶されなかった選択”を逆照射するためのマッピング装置でもある。
仮説1:自ら飛び込んだ存在──これは“遊び”なのか?
これは最も楽観的なシナリオだ。
あなたは、現実世界のどこかで、意識的にこの世界に入った。
目的は娯楽か、学習か、あるいは体験としての“生”。
記憶は一時的にロックされており、旅が終われば、元の現実に戻る──
まるで、超高精度のVRゲームのように。
この説の魅力は、“自由意思”を前提としている点にある。
あなたは選んだのだ、自らここに来ることを。
しかし、ここには一つの根本的な矛盾がある。
では、なぜ覚えていない?
「体験をリアルにするために記憶を消した」?
それは説明ではない。仮説を証明するために都合よく記憶を剥奪する構造は、検証を拒否する装置そのものだ。
これでは、思考を麻痺させるだけの言い訳だ。
さらに言えば──
我々がこの世界を“苦しみ”や“無知”とともに生きている理由を、どのように正当化する?
自ら飛び込んだ旅にしては、あまりに残酷で、あまりに説明がなさすぎる。
仮説2:閉じ込められた存在──ここは“牢獄”なのか?
これはマトリックス型の世界観だ。
あなたは、何者かによってこのシミュレーションに閉じ込められた。
監視、抑制、記憶の改ざん──この世界は“真実”から遠ざけられるように設計されている。
この説には一種の“整合感”がある。
なぜなら、我々が経験する違和感、矛盾、制限がこの仮説とよく符合するからだ。
- なぜ思い通りにいかないことが多いのか?
- なぜ“死”が明確にプログラムされているのか?
- なぜ世界は「知りすぎると不快になる構造」を持っているのか?
だがこの仮説には、根拠となる“閉じ込めた存在”が描けないという致命的な欠点がある。
- 誰が?
- なぜ?
- どうやって?
それを説明できないまま「陰謀論的閉鎖空間」に着地すれば、思考停止の寓話になる。
仮説2は、信じたくなるが、**最も証明が難しい“可能性の檻”**だ。
仮説3:最初からここにいた──あなたは、造られた存在なのか?
これは──最も淡々としていて、最も寒々しい仮説だ。
あなたは、自ら選んでここに来たわけでも、誰かに囚われたわけでもない。
初めからこの世界の一部だった。
それは、ゲームのNPC(ノンプレイヤーキャラクター)のような存在だ。
自己認識を持っているが、それがどこから来たのかは分からない。
“現実”という言葉さえ、このシステムの中で定義されている。
この仮説が示すのは、「現実に行く」という選択肢すら持たない存在である自分」だ。
──そして、最も残酷なのは、この仮説が最も整合的であるという事実だ。
- なぜ生まれた瞬間からこの世界の“ルール”を内在化しているのか?
- なぜどんなに思索しても、決定的な“外部”に手が届かないのか?
- なぜこの宇宙は、まるで意識に最適化された“舞台”のように整っているのか?
宗教という概念の早すぎる登場。
数式で記述される物理法則。
整いすぎた初期値を持つ宇宙の始まり。
それらすべてが「この世界は最初から設計されていた」という可能性を示している。
では、あなたはどの仮説を“本能的に”感じただろう?
選んだ?
閉じ込められた?
それとも、最初からいた──?
この3つのどれに自分が当てはまるのかを考えることは、「自分という存在を、設計図として捉える」第一歩なのかもしれない。
次章では、宗教という人類最古のプログラムに潜む“初期化コード”を読み解いていく。
あなたが「最初からいた存在」だとするならば、その証拠は、思考のもっとも深い場所に記録されているはずだ。
第3章:神のコード──宗教という“初期設定”
「最初に人間が発見したものは、神ではない。神という概念そのものが、最初から“発見されるように”設計されていたのだ。」
火よりも先に、神を想像した。
車輪よりも先に、天を見上げた。
──それが人類という存在の“不自然な初期条件”だった。
石器を持つより早く、「見えない存在」を語り始めた私たちは、まるで自分より上位の存在を探すように設計されていたかのようだった。
「何かが在る」という前提の不自然さ
自然界を観察したとき、人類は驚くべき前提を持っていた。
「この世界には“始まり”があり、“意味”がある」と。
なぜ?
なぜ、ただの出来事を“意味ある創造”と受け取ったのか?
なぜ、雷鳴や日食や病気を、“誰か”の意思だと考えたのか?
それは、“意味付けする知性”の出現が、単なる進化の産物ではなく──あらかじめ設計された起動処理だった可能性を示している。
人は、生まれながらにして「上を見る」ように設計されていた。
重力に逆らい、天に向かって塔を立て、自分が誰かに“見られている”という感覚に怯えるように。
宗教は“設計主”を探すための装置だったのか?
神とは、いったい何なのか。
支配者?
裁き手?
救済者?
それよりも先に、「創造者」だった。
あらゆる宗教の根底には、“世界をつくった誰か”の存在が前提されている。
それはまるで、この現実が“誰かによって始められた”というコードが、すでに我々の認知構造に焼き込まれているかのようだ。
そしてこのコードは、宗教だけにとどまらない。
- ビッグバン理論:始まりがあるという前提
- 創造神話:言葉と光による起動
- 終末思想:この世界が“閉じる”という設計構造
科学でさえ、「開始と終了のある宇宙」を前提にしている。
その前提がすでに、作為的ではないだろうか?
進化か、埋め込まれた認知か
「それは進化の産物だ」と言う人がいる。
恐れによって団結し、死の意味を物語に変え、目に見えない存在によって秩序を保とうとした──
たしかに、宗教は社会的秩序装置として機能してきた。
だがそれは**「宗教が人を作った」のか、「人が宗教を求めるよう設計されていた」のか**を逆転させるロジックにもなり得る。
進化論で説明できるのは「なぜ信じるか」だが、シミュレーション仮説で問うのは「なぜ“その発想を持った知性”が発生したのか」である。
それは、プログラムの自己保守機能のようにすら見える。
「信仰」の構文と、「創造者」の仮定
宗教の共通構文には、以下の要素が含まれている:
- 世界は誰かによってつくられた
- 人間は目的を持ってつくられた
- 生の終わりには評価または転送がある
これはまさに、プログラムの基本構成と一致する。
- 初期化(Creation)
- 実行(Execution)
- 終了時処理(Termination)
そして特筆すべきは、宗教が“この世界以外の層”を常に想定していることだ。
天国、地獄、浄土、黄泉、輪廻、来世──
どの文化においても、「この世界は一時的なものである」という暗黙の共通認識が存在する。
仮想世界には仮想世界の“外”がある、という発想だ。
それが宗教として表出した可能性は、否定できるだろうか?
「祈り」は誰に向けられているのか?
祈りとは、誰かに向けた通信である。
しかし──
その“誰か”が一度も返信してこないとしたら?
その“存在”が、むしろ我々が想定するように設計されたインターフェースだとしたら?
つまり、祈りとは**「上位存在がいることを前提とした通信」**であり、
その存在がいるかどうかではなく、“そう思うように設計されている”ことこそが本質なのだ。
我々が神を創ったのではない。
我々が「神を想像するように」創られている。
これは信仰ではなく、構造の話だ。
あなたが「神など信じていない」と思っていても、あなたの脳は神の構文で動いているかもしれない。
そして、それは「あなたがシミュレーションにいる」という最も確かな痕跡の一つだ。
次章では、**この世界の“数式的な精密さ”**がどのようにこの仮説を補強するのかを掘り下げる。
あなたが信じてきた「物理法則」そのものが──
誰かのコードかもしれない。
第4章:物理の彼岸──この世界は「数式」でできている
見えるすべては、触れることができても、解像できない。なぜならこの世界は、“モノ”ではなく、“意味”でできているからだ。
石を手に取れば、冷たく重い。
水に手を入れれば、温度と流動性がある。
──けれど、それらの正体を数式で記述できてしまうという事実を、我々は疑わない。
重さも、色も、時間も、距離さえも。
あらゆる現象が「計算」で記述可能であるということ。
それこそが、最も不自然な“自然”ではないか?
神の言語は“数学”である
宇宙という書物は、数学という言語で書かれている。
この言葉は長らく「比喩」として扱われてきたが、
今やそのまま「構造」として受け止めるべきかもしれない。
我々がこの世界の成り立ちを理解しようとしたとき、辿り着くのは物質ではなく、数式である。
- 相対性理論:時空と質量が滑らかに変形する数式
- 電磁気学:光や電波が波として伝わる関数
- 熱力学:分子の運動を確率的に記述する数式
──これらの法則に、“意味”は必要ない。
ただ数式だけが、現象を完璧に再現する。
なぜ世界は、意味ではなく、数式で再現可能なのか?
なぜ、**“この世界の裏側には、計算可能な秩序がある”**という前提が成立してしまうのか?
その問いの裏に、「最初から設計されたコードが存在する」という可能性が立ち上がる。
物理法則は「発見」ではなく「仕様書」かもしれない
科学者たちは「この宇宙の法則を発見した」と語る。
だがそれは、誰かが書いた“仕様書”を解析しているだけかもしれない。
- なぜ重力は“この強さ”なのか?
- なぜ光速は“この速さ”なのか?
- なぜ素粒子の種類は“この数”なのか?
これらには理由がない。
すべて「そうであることにしておく」ことで、世界は破綻せずに回っている。
ここにあるのは、「偶然」ではなく構成された整合性。
まるで、動作条件を満たすパラメータで世界がチューニングされているような感覚──
それを、理論物理学者たちは**“ファイン・チューニング問題”**と呼ぶ。
つまり、この世界は“動作するように設計された仮想環境”かもしれないという考え方が、すでに物理学の最前線で静かに浮かび上がっている。
情報宇宙──「すべてはビットである」
MITの宇宙論者マックス・テグマークはこう語った。
「この世界がここまで数学的に美しいのは、我々が“コードの中”にいるからかもしれない」と。
さらに理論物理学者ジョン・ホイーラーは、「It from bit(全ての存在はビットから来る)」という言葉を残している。
これはつまり、物質もエネルギーも、最終的には**“情報”の塊**だという考え方だ。
- 「存在する」とは、情報が定義されていること
- 「運動する」とは、情報が書き換えられていること
- 「死ぬ」とは、情報の更新が終了すること
この仮説を受け入れるならば、**我々は「物質」ではなく、「データ構造」として存在している」ことになる。
そしてそれは、あまりにシミュレーション的すぎる。
エラー訂正符号──宇宙に組み込まれた“保守ロジック”
2010年、理論物理学者ジェームズ・ゲイツは、超対称性理論の数式を研究する中で
エラー訂正符号──つまり、デジタル通信に使われるエラー耐性のある構文が自然界の式の中に組み込まれていることを発見した。
「これは偶然では説明がつかない」と、彼自身が語っている。
- エラー訂正は、壊れた信号を復元するための仕組み
- それが自然界の根本式に“初めから組み込まれている”
──もし宇宙がハードウェアで動いているとしたら、この発見は、そのBIOSのようなものかもしれない。
宇宙がエラーを自動で修正するように設計されている。
それは、誰かが“クラッシュしない世界”を作ろうとした痕跡かもしれない。
では、なぜこの世界は“数式的”なのか?
答えは1つしかない。
その方が“扱いやすいから”だ。
数式は再現性があり、演算可能で、整合性がある。
そして、外部からの観測者にとって、**最も「制御しやすい形式」**でもある。
我々がこの世界を理解できるのは
この世界が「理解されるように」作られているからだ。
もしあなたが、空の動きや音の反響に「なぜか美しさ」を感じるなら、それはこの世界が、あなたの知覚に最適化された“設計物”だからかもしれない。
重力があなたを地に引き戻すのと同じように、
この世界の数式は、あなたの思考を“内側”に引き戻してくる。
だが次章では、その内側で最も奇妙な領域──
「観測するまで存在しない」ものたち、
つまり量子が見せる演算の裏側を覗いていく。
それは、**この世界の「未レンダリング領域」**に触れる旅でもある。
第5章:実験と矛盾──仮想現実のバグを探す者たち
「観測されるまでは存在しない」そんな世界が、“現実”であるはずがない────だが、現実は、そうなっている。
この世界は完璧に見える。
だが、完璧な世界ほど、“バグ”は深く隠されている。
そしてバグは、いつも“境界”で見つかる。
計算の限界、認識の限界、そして──観測の限界。
そう、世界最大の違和感は「観測」にある。
なぜなら**「見られるまで存在しない」**というルールは、
まるで“演算の節約”のように感じられるからだ。
二重スリット実験──観測されると振る舞いが変わる世界
量子力学が提示する、最も悪質で美しいパラドックス。
それが「二重スリット実験」だ。
電子を1個ずつスリットに通す。
観測しなければ、干渉縞が現れる(波として振る舞う)。
観測すると、干渉縞が消え、粒子の振る舞いになる。
この現象を、「観測されたことによって波動関数が崩壊した」と説明するのが量子論の標準的理解だが、
よく考えてほしい。
それは、あまりに「都合が良すぎないか?」
「見るまで存在しない」「見た瞬間に結果が確定する」
──この世界は、まるで“観測に応じてリアルタイムで計算される仮想世界”のようだ。
それはまさに、ゲームエンジンが**“カメラの範囲外のグラフィックを描画しない”**ような仕様に酷似している。
観測=トリガー説──この世界は“未レンダリング領域”を持っている?
もし世界がシミュレーションであるなら、無限の演算を回避するために「必要な部分だけ計算する」仕様があってもおかしくない。
この仮説に基づいて、カリフォルニア工科大学のフーマン・オワディらは、
量子スケールの手抜き計算を暴こうとした。
彼らは以下のようなシナリオを想定した:
- 「観測されるまで処理をスキップしている」なら、
あえて計算負荷の高い状態を予告なく測定すれば“反応遅れ”や“矛盾”が出るのでは? - 「観測がシステムを決定させている」なら、
同時に異なる角度から観測すれば処理の競合が起きるのでは?
これらは理論段階に留まっているが、目的は明確だ──シミュレーターの手抜きを暴くこと。
まるで、壁を叩いて“空洞の音”を確かめようとするような試みだ。
宇宙線のカットオフ──システムの“上限”があるかもしれない
ボン大学の物理学者シラス・ビーングらは、宇宙線の観測データに注目した。
超高エネルギー宇宙線のスペクトルには、**“GZKカットオフ”**と呼ばれる現象が存在する。
あるエネルギーを超えると、観測される粒子の数が急激に減少するのだ。
これは通常、宇宙背景放射との相互作用による減衰とされる。
しかし彼らは別の仮説を立てた。
「もし宇宙が格子状にシミュレートされているなら、あるエネルギー以上の粒子は“格子を越えてしまい”、観測できなくなる」
──つまりこれは、宇宙が持つ「処理限界の兆候」かもしれないというのだ。
ただし現時点では、これは“かもしれない”に過ぎない。
GZKカットオフは他の理由でも説明できるし、決定的な証拠とは言えない。
だが、それでも──
「そう考えると“しっくりくる”構造がそこにある」ということ自体が、思考のバグなのか、システムのバグなのか、判断を曖昧にする。
世界は観測によって“生成されている”?
この章であなたが感じた違和感は、こう言い換えることができる:
世界は、存在しているのではなく、「観測に応じて実行されている」
これが意味するのは
我々が知覚する世界は、“常に確定しておらず”、仮に確定するとしても“誰かが見るその瞬間”であるということだ。
もし仮想世界が「効率よく動くこと」を目的として設計されているなら
**“未観測の部分を計算しない”**という仕様は非常に合理的だ。
これはもはや哲学的思索ではない。
現実世界の設計原理に対する、科学的な“刺突”である。
この世界の“綻び”を探す者たちは、信じているわけではない。ただ、「完璧すぎる」ものに、何かが隠されていると知っているのだ。
次章では、こうした違和感がやがて一つの哲学的帰結へと向かう構造を見ていく。
すなわち、「この世界は偽物でも、それが“悪いこと”とは限らない」──
そんな、存在そのものに対する認知の反転へ。
第6章:存在するという嘘──「現実ではない」が、現実であるという論理
「あなたが生きているこの世界が、もし“作り物”だったとして──それは“無意味”なのだろうか?」
ここまで読み進めたあなたには、もはや「我々の世界が仮想であるかもしれない」という前提に、さほど抵抗がなくなってきているはずだ。
でも、ひとつだけ立ち止まって考えてほしい。
仮にそうだとして──
それが、何なのだろうか?
「現実」の定義は、誰が決めるのか?
デイヴィッド・チャーマーズ。
NY大学の哲学者であり、意識のハードプロブレムを提唱した彼は、こう言った。
「たとえ私たちの世界がシミュレーションだとしても、それは“現実ではない”ことを意味しない」
この発言は、世界観を根底から覆す。
なぜなら、“現実かどうか”を決めているのは、構造ではなく経験だと彼は主張しているからだ。
- この世界に触れた感覚が本物ならば
- この世界に悲しみや喜びがあるのならば
- そして、この世界で“選択”が行われるのならば
それは現実として扱うべきである──と。
つまり、現実とは「本物か偽物か」でなく、「どれだけ真剣に生きたか」によって成立するものだという逆転。
この論理の裏には
「現実」の定義すらもまた、構築されたルールであるという視点が潜んでいる。
「虚構であってもリアル」という存在論的パラドックス
ここで、ある寓話を思い出そう。
夢の中で蝶になった荘子。目覚めて人間に戻ったとき、こう問う。「夢で蝶だったのか? それとも今、人間を夢見ている蝶なのか?」
この物語の本質は、“真実の側”を決めることの不可能性だ。
どちらも「体験」はリアルだった。
そしてそれこそが、**「現実の唯一の証明手段は主観である」**という絶望的な前提を示している。
さらにチャーマーズはこうも語る。
「私たちがベースリアリティにいる証拠は決して得られない。なぜなら、すべての証拠はシミュレーション内で生成される可能性があるからだ。」
これは、あらゆる“外部証明”を拒否する“論理の檻”だ。
──けれど、これは同時にひとつの救済でもある。
なぜなら、“絶対的な現実”に到達できないならば
「今ここにある主観的現実」を最大限に生きるしかないという意味でもあるからだ。
シミュレーションだからこそ可能な“意味”がある
もし世界がプログラムされたものだとして──
それは「意味がない」のではなく、むしろ**「意味を注入できる余白がある」**とも言える。
ゲームの中のキャラクターは、自分がデジタルであることを知る必要はない。
むしろ、彼らのドラマや選択は、“物語としての真実”を宿している。
我々もまた、選択を通じて自分の“現実性”を確定させている存在なのかもしれない。
- あなたが傷ついたとき
- 誰かを愛したとき
- 迷い、苦しみ、でも何かを選んだとき
たとえその世界が偽物であっても
その痛みと決断は“本物”として残り続ける。
そして、存在は証明される──あなたが“疑った”という事実によって
デカルトは「我思う、ゆえに我あり」と言った。
だがシミュレーション仮説はその逆を問う。
「もし全てが作り物であっても、“それを疑う自分”は、どこから生まれたのか?」
あなたが「ここは仮想世界かもしれない」と思った瞬間
あなたの意識は“外部を想定する能力”を発動したことになる。
つまり、“外部がある”という証明にはならなくても
“外部を意識する機能”が搭載されているという事実は残る。
それはつまり
あなたが単なる演算処理ではなく、選択の責任を持つ存在として設計されていることの証だ。
そして──
この章で最も奇妙な事実はこれだ。
「この世界がシミュレーションかもしれない」と考えている時点で、あなたはそのプログラムの設計構造に気づき始めている“存在”であるということだ。
次章では、そんな「気づいてしまった者」が、この現実をどう扱うべきかという問いに向き合う。
世界がコードでできていようと、虚構であろうと、それを“自分のもの”に変えるかどうかは、あなた次第だ。
第7章:終端の選択肢──あなたが“意味づける”という現実
世界が“本物”かどうかは、もはや問題ではない。問われているのは──**あなたがその世界を“どう意味づけるか”**だ。
ここまで辿ってきた道のりは
「この世界が仮想かもしれない」という知的スリルだけで構成されてはいない。
むしろ、問いは最終的にあなた自身へと跳ね返ってくる。
- あなたはどんな世界を現実として扱うか。
- 何に対して信頼を置き、何を疑うのか。
- そして、どんな意味を“自分の現実”に与えるのか。
それは誰かに与えられるものではない。
あなたの“選択”こそが、あなたの“現実”になる。
意味は上から降ってこない。あなたが与えるものだ。
ここまでで繰り返し示されてきたのは
この世界があまりにも“よくできすぎている”という事実だ。
整いすぎた数式。
都合のいい観測法則。
信仰を前提にした認知構造。
そして、違和感すらプログラムの一部に思えるような仕様。
つまり、この世界は**“意味を持たせやすいように作られている”**のだ。
だが、それが「意味を持つ世界だ」という保証にはならない。
あなたが意味を付与しなければ、それは単なる背景に過ぎない。
虚構でも、愛したなら、それは現実だ。
たとえあなたがシミュレーションの中にいたとしても、
そこで経験した感情、交わした言葉、失ったもの、救われた瞬間──
それらすべてが**“真実だった”と言えるかどうか**は、あなた自身の解釈にかかっている。
物語の主人公は、自分の世界の構造を知ったとき、絶望ではなく、意志によって“自分の物語”に意味を与え直す。
──この世界も、同じだ。
意味を“かたち”にして残すということ
この章が終わったあと、あなたは何も持たずにこのページを閉じることもできる。
けれど、もし──
この読書体験に何か輪郭のある余韻を残したいと願うなら。
それは言葉かもしれない。
沈黙かもしれない。
あるいは、ある感情の重みかもしれない。
それがどんなものであれ、
あなたが「意味があった」と思った瞬間、その瞬間だけは確かに、この宇宙に存在していた。
世界が虚構であっても、あなたが「これは残したい」と思ったなら、それはもう、**誰にも消せない“現実”**だ。